市議会での、議員と市役所の答弁を聞いたことはありますか?
多くの人にとってはあまり知られていないかもしれませんが、そこでは私たちの今後の生活に役立つ情報がたくさんあります。議員たちの意見を聞くことで、次の選挙で参考になるヒントが得られることもあります。
今回は、令和6年11月議会で話題になった「不登校問題」について紹介します。
不登校問題とは
不登校問題は、日本の教育現場で深刻化している課題です。2023年度の文部科学省の調査によると、小中学校の不登校児童生徒数は過去最多の34万6482人に達し、前年度から15.9%増加しました。これは11年連続の増加となります。
不登校の主な要因には、学校生活へのやる気の欠如や不安・抑うつなどが挙げられています。
市議会での答弁を見てみよう!
 議員
議員【議員】
まず、市の現状をお伺いします。
市内小中学校の不登校児童生徒数、別室登校、教育支援センターの利用状況を詳細データで教えてください。
全国と比較した松阪市の状況もお願いします。
【市役所】
令和5年度、県全体で不登校は4568人と増加しましたが、松阪市は小学校179人、中学校258人、計437人と9人減少。
別室登校は256人、支援センターは47人利用。



【議員】
今年度で3年目のいきいき学校プロジェクトの成果と課題をお聞かせください。
【市役所】
令和5年度、不登校は9人減少し、学校での児童の学級満足調査では、満足度群は67%(全国平均42%)。いじめ件数も401件から238件に減少。
相談件数は27787件、不登校生徒の89%が繋がり、50.8%に改善が見られました。
課題は長期不登校の増加です。
令和5年度、欠席日数が90日以上の長期の不登校の状態にある児童生徒が241人おり、不登校児童生徒全体の55.1%と、令和3年度の47.4%、令和4年度の50.4%から増加をしております。
教育委員会としては、不登校の未然防止の取組や校内の居場所づくり、学校内外の居場所との連携を引き続き進めるとともに、指導や支援につながりにくかったり、欠席日数が多くなったりしている子どもや保護者への積極的な支援進めてまいります。
親としてはどう向き合うべきか
親が不登校の子どもに対して取るべき対応は、まず子どもの気持ちを尊重し、無理に登校を促したり問い詰めたりしないことが大切です。
家庭を安心できる居場所にし、子どもの話を否定せずに受け止め、本人が話し出すのを待つ姿勢を持ちましょう。
また、親自身も焦らず、学校や専門家、支援団体と連携しながら情報を集め、必要に応じて相談することが重要です。家庭だけで抱え込まず、周囲のサポートも活用しましょう。

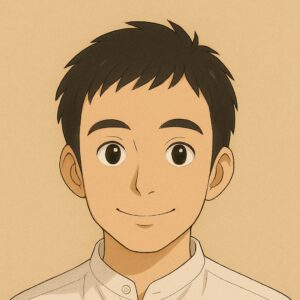




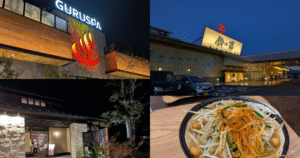



コメント