令和6年10月に行われた、津市初の空家撤去に係る略式代執行について、解説します。
なお、本記事は、記者発表資料、市議会の議事録、工事に係る入札公告などの情報を基に作成しています。
目次
略式代執行とは

空き家問題が深刻化する中、特に危険な状態にある空き家に対して自治体が取る最終手段が「略式代執行」です。
これは、所有者が不明または相続放棄などで所有者が存在しない場合に、周辺住民や通行人に被害が及ぶ恐れが切迫していると判断された特定空家等について、市町村長が空家等対策特別措置法(空家法)第22条第10項に基づき、除却(解体)などの措置を行うものです。
特定空家等とは、放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる、または衛生上有害となる状態、適切な管理がされず景観を損なっている状態など、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすと認められる空き家を指します
略式代執行に至るまでの経緯
今回の津市の事例では、まず地元自治会から老朽化した空き家について市に相談が寄せられました。
現地調査の結果、屋根の崩落や瓦の落下、外壁材の飛散など、周辺住民にとって危険な状態であることが判明し、特定空家等に認定。市が所有者に対して改善を求める通知を行い、以降も定期的なパトロールを実施してきました。
しかし、所有者が亡くなり、相続人全員が相続を放棄したことで所有者不存在となりました。その後も建物の劣化が進み、倒壊や道路閉塞の危険性が高まったため、市は略式代執行による除却を決断しました。
津市での初事例とその背景
場所
津市で初めて実施された略式代執行の現場は、民家が密集する地域に位置し、外見からは分かりにくいものの、屋根の崩落や内部の朽廃が著しい危険な空き家でした。


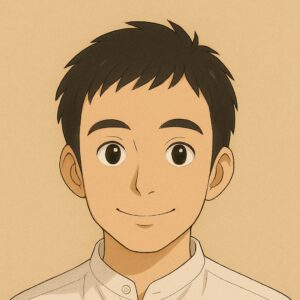








コメント